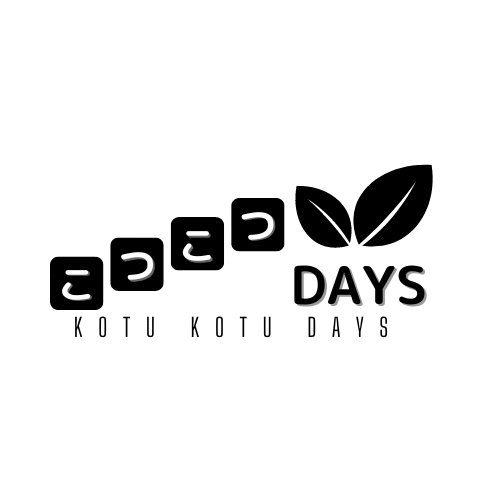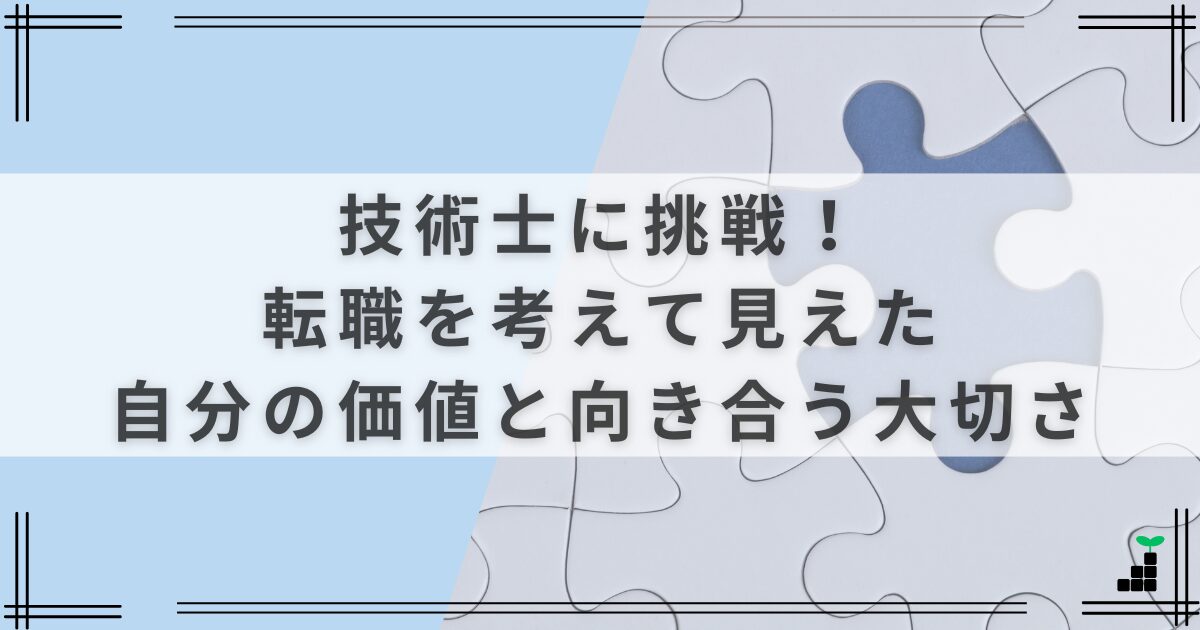【挑戦】技術士一次試験を価値ある学びに|基礎・適性科目の必要性
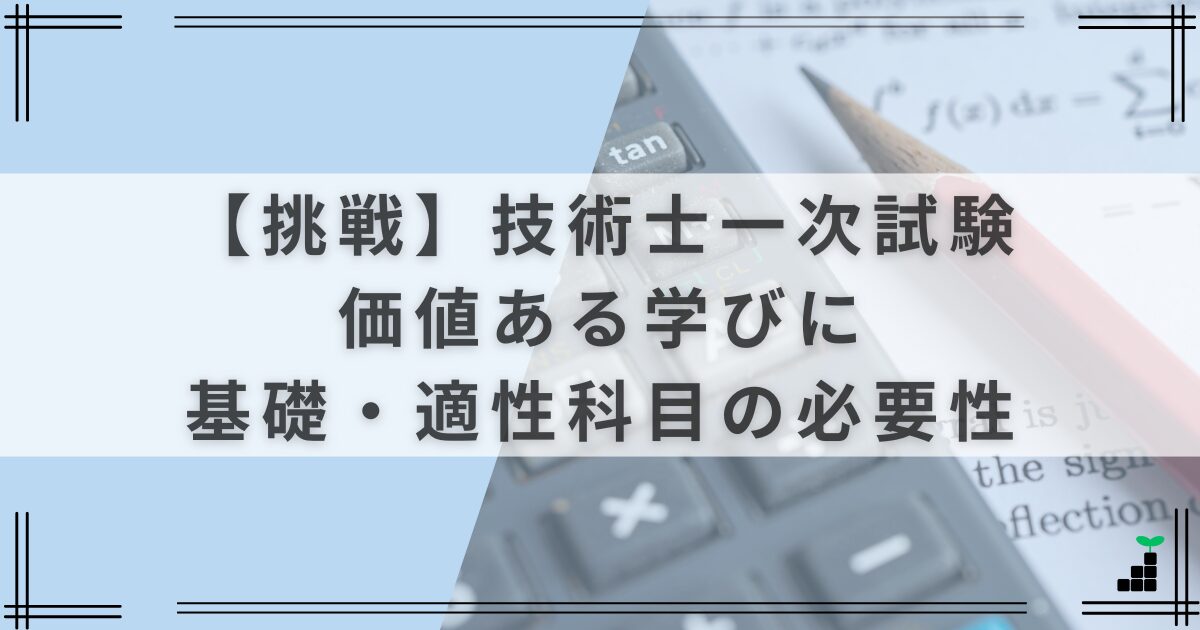
「技術士の一次試験の勉強、そろそろ始めようかな」
そんなふうに思いながらも、何から手をつけたらいいか分からないという方もいらっしゃると思います。
私自身、転職やキャリアのことを考える中で「もっと自分の価値を高めたい」と思い、技術士に挑戦することを決めました。
でも、ただ合格を目指して暗記するだけでは、意味がないとも感じています。
これから勉強していくうえで、せっかくなら「使える知識」「役立つ学び」にしたいと思っています。
この記事では「一次試験の概要」に加えて、技術士にとって「なぜ各科目を学ぶのか?」という“学ぶ意味”についても共有したいと思います。
最初に勉強の目的をしっかり意識することで、ただ覚えるだけの勉強ではなく、「自分にとって価値ある学び」に変えていけると思っています。
技術士一次試験の概要
「技術士」ってどんな資格?
簡単にいうと、科学技術に関する専門知識を持ち、それを社会に役立てられる国家資格です。
単なる資格というよりも、“信頼される技術者”であることを証明する肩書き。
企業や行政との関わり、技術的な提案、マネジメントなど、実際の仕事でも活かせる場面が多く、「一目置かれる存在」として認識されることも。
特に近年は、社会課題の解決や持続可能な開発(SDGs)への貢献も求められており、技術士の役割はより大きくなっています。
まず、技術士になるための最初のステップが「一次試験」になります。
一次試験⇒二次試験(筆記試験・口頭試験)⇒技術士
試験の構成
| 試験区分 | 出題内容 | 合格ライン |
|---|---|---|
| 基礎科目 | 技術者に必要な基本知識(5分野) | 50%以上 |
| 適性科目 | 技術者としての倫理観や考え方(技術士法第4章が中心) | 50%以上 |
| 専門科目 | 自分の選んだ専門分野に関する知識 | 50%以上 |
基礎科目:技術者の“土台”になる5つの分野
- 設計・計画に関するもの
→ モノづくりの基本。どう形にするか?を考える力。 - 情報・論理に関するもの
→ データを扱う力+筋道を立てて考える力。 - 解析に関するもの
→ 数学的に現象を読み解くスキル。 - 材料・化学・バイオに関するもの
→ 技術を支える「素材」の知識。理系的基礎力。 - 環境・エネルギー・技術に関するもの
→ サステナブルな視点を持つ技術者になるために。
適性科目って何?
意外と見落とされがちだけど、超重要なのがこの適性科目。
主に「技術士法第4章(技術者倫理や責務)」に関する問題が出されます。
「自分の技術が社会にどう影響するか」をちゃんと考えられるか?
っていう、技術者としての姿勢や考え方が問われます。
なぜ基礎科目が必要か?(土台の力)
技術士にとって「基礎科目が必要な理由」を考えながら勉強することで、より実践に役立つ知識として定着すると思います。
① 専門家ほど“視野の広さ”が問われる
技術士って、ただのスペシャリストじゃなくて、社会の中で技術を使う“責任ある専門家”です。
だからこそ、「狭く深く」ではなく、
“広く浅くてもいいから、技術全体のつながり”を知っておく必要があります。
たとえば、「設計・計画」と「環境・エネルギー」って、本当は密接に関係してたりします。
安全性や環境負荷を無視して設計する技術者であってはならないということだと思います。
② チームで働くには“共通言語”が必要
現場では、いろんな分野の技術者と関わります。
材料の専門家、情報系のエンジニア、環境の担当者…。
その時に「他分野の基本的な知識」がないと、話がかみ合わないこともあると思います。
基礎科目は、“技術者同士の共通言語”を学ぶイメージ。
たとえば、専門用語や「材料の劣化をどう捉えるか」「エネルギー効率は?」といった話、最低限はわかっていないと議論することもできなくなってしまいます。
③ 技術士は“問題発見・解決”のプロ
技術士って、「問題を発見して、解決に導く人」。
そのためには、問題をいろんな角度から見れる思考力が必要。
基礎科目の「解析」「情報・論理」あたりはまさにそれを養うためのもの。
論理的に考えたり、仮説を立てて検証する力って、どの分野でも共通して求められます。
④ 社会全体を見渡せる“技術のバランス感覚”を育てる
たとえば、ある技術がコスト面で優れていても、環境負荷が大きかったらどうしますか?
→その判断を下すときに役立つのが、基礎的な環境・エネルギーの知識。
「何を優先すべきか」「バランスはどうか」を考えるための“引き出し”が、基礎科目で得られるというわけです。
基礎は「土台」であり「地図」
基礎科目は、以下のようなものだと思います。
- 専門を活かすための土台
- 技術の全体像を俯瞰する地図
これがあるから、技術士は「専門家だけ」じゃなく、「信頼される技術者」として活躍できると思います。
なぜ適性科目が必要か?(技術者の資質)
① 技術者としての“社会的責任”を理解するため
技術士は、単に「技術力が高い人」ではなく、
社会や環境への影響を意識して判断・行動できる人であることが求められます。
- 安全性や環境保全の視点を持たずに技術を使えば、人の命や暮らしを脅かす可能性もある
- 倫理的に問題のある判断(データ改ざんなど)をしたら、企業や社会に大きな損害を与える
こうしたことを未然に防ぐために、法的・倫理的な知識や技術者としての責任感が必須。
それを問うのが「適性科目」なんだね。
② 技術士法や関連制度の理解が“実務”で必須だから
適性科目では、技術士法の第4章(義務・責務)や、関連する法令・制度の理解が求められます。
- 技術士は「公益の確保」や「守秘義務」が法で定められている
- 資格を使って技術士CPD(継続教育)などの義務を果たす必要がある
- コンプライアンス、品質保証、リスクマネジメントなども重要な役割の一部
「資格を取ったら終わり」ではなく、取ったあとに果たすべき“社会的な役割”を知るための科目なんだね。
③ 技術と社会をつなぐ“橋渡し役”としての視点を持つた
技術士は、専門技術を「社会の課題解決」にどう活かすか?を考える立場です。
だから、専門知識だけでなく、以下の点も欠かせません。
- 社会全体の視点(倫理、法律、環境、安全など)
- ステークホルダーとのコミュニケーション力
適性科目は、技術者としての“視野の広さ”と“俯瞰的な思考”を問うともいえますね。
適性科目は、「技術を使う人」から「技術を通じて社会に貢献する人」になるために必要!
技術士ビジョン21とは
技術士ビジョン21は、日本技術士会が平成16年6月に策定した、技術士のあり方や役割、使命などを示した指針です。
「技術士になること」がゴールではないと思います。
その先で、どんな風に社会と関わり、価値を提供していくか?
「技術士ビジョン21」は、その道しるべになる考え方です。
この視点を持ちながら勉強することで、資格を“飾り”にせず、“武器”として使える知識になると思います。
① 社会からの信頼を得る
- 単なる資格者ではなく、倫理観と責任感を持って行動するプロであることが求められる
- 「技術は社会のためにある」という前提が大切
② 絶えず学び続ける技術士
- 社会や技術は日々変化している
- 自己研鑽(CPD:継続的能力開発)を行うことが必須
- 学び続けることで、“時代に通用する技術士”に
③ 社会的課題への対応力
- 環境問題、災害リスク、少子高齢化、エネルギーなど…
- そうした複雑で多様な課題に対応できる力が技術士に求められる
- 単なる専門知識だけではなく、広い視野で問題解決にあたることが必要
④ 多様な分野との連携
- 技術士は専門家でありながら“橋渡し役”でもある
- 他分野の人や社会と協働し、共に解決策をつくっていく姿勢が大切
⑤ 国際社会でも通用する
- 日本だけではなく、グローバルな視点で物事を考える
- 国際基準や海外との技術協力も視野に入れる
技術士ビジョン21を知ることで得られる視点
| ポイント | ただの資格者 | 活かせる技術士 |
|---|---|---|
| 資格の意識 | 資格を持つことがゴール | 社会に貢献する手段 |
| 学びの姿勢 | 試験が終わったら終わり | 常に学び、成長する |
| 問題への視点 | 専門知識に偏る | 社会課題とつなげて考える |
| 行動の軸 | 自分中心・自己完結 | 倫理観を持ち、他者と協働 |
今後の勉強 ~使える知識にするために~
これから、一次試験に向けて過去問を中心に勉強していこうと思っています。
ただ、単に問題を解いて答えを覚えるだけでは、試験が終わったら忘れてしまうし、「本当の意味で理解した」とは言えないと思います。
だからこそ、「使える知識」として自分の中に根づかせることを目指して勉強していきたいと考えています。
そのために、以下のようなことにも目を向けながら、ただの暗記ではなく、納得しながら学べるように意識して取り組んでいくつもりです。
- なぜこの問題が出題されているのか
- どんな背景や考え方があるのか
- 関連するキーワードや分野は何か
また、学んだことを自分の言葉でアウトプットすることで、記憶の定着もぐっと高まると言われています。
なので、ここでも定期的に過去問の解説や学びの気づきを発信していけたらと思っています!
もし、同じように技術士を目指して頑張っている方の参考になったり、「ちょっとやってみようかな」と思ってもらえるきっかけになれたら、嬉しいです!